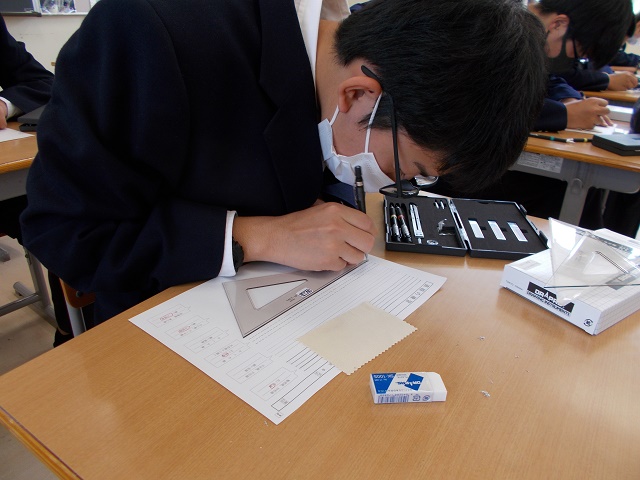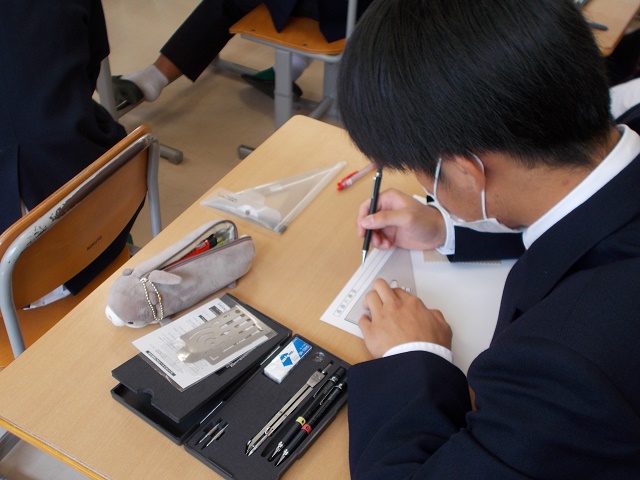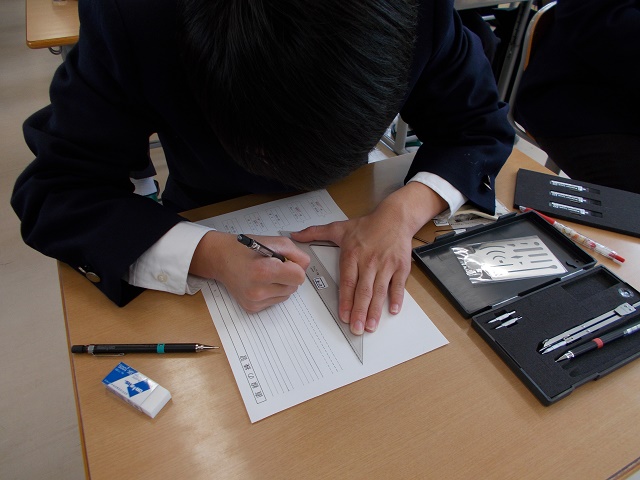本日5,6時間目の課題研究の時間に各専攻で行っていることを紹介します。
🌸草花専攻🌸
ペチュニアの交配をするために色違いの花を選んでいる様子です。どの花にするかよく考えながらえらんでいました。どのような花ができるのか楽しみです。  この写真は前回紹介した再利用したホースを尖っている部分に使用し保護している様子です。うまくつけれるように丁寧にホースに穴を開けたり、くくりつけていました。出来上がったところをまた載せたいと思います。
この写真は前回紹介した再利用したホースを尖っている部分に使用し保護している様子です。うまくつけれるように丁寧にホースに穴を開けたり、くくりつけていました。出来上がったところをまた載せたいと思います。


🍇果樹専攻🍇
この写真はブドウ(シャインマスカット)の摘穂をしている様子です。今年伸びた枝1本につき1本の花穂が着くように余分な花穂をハサミで切って取り除いていきます。これもブドウが大きく成長すつために欠かせない作業です。

ブドウ(高妻)の花穂整形をしている様子です。花振るい防止、品質安定のために行っている作業です。一人で膨大な数の作業をしていますが、一生懸命頑張っています。実ができるのが楽しみですね。


🍈セラピー専攻🍈
この写真はメロンの摘心とフック掛けの様子です。摘心はメロン1つ1つに栄養を行き渡らせるために行うそうです。フック掛けとはフックを掛けているところにいいメロンがなるため目印を付けているそうです。


写真・文章:3H 青井 原田