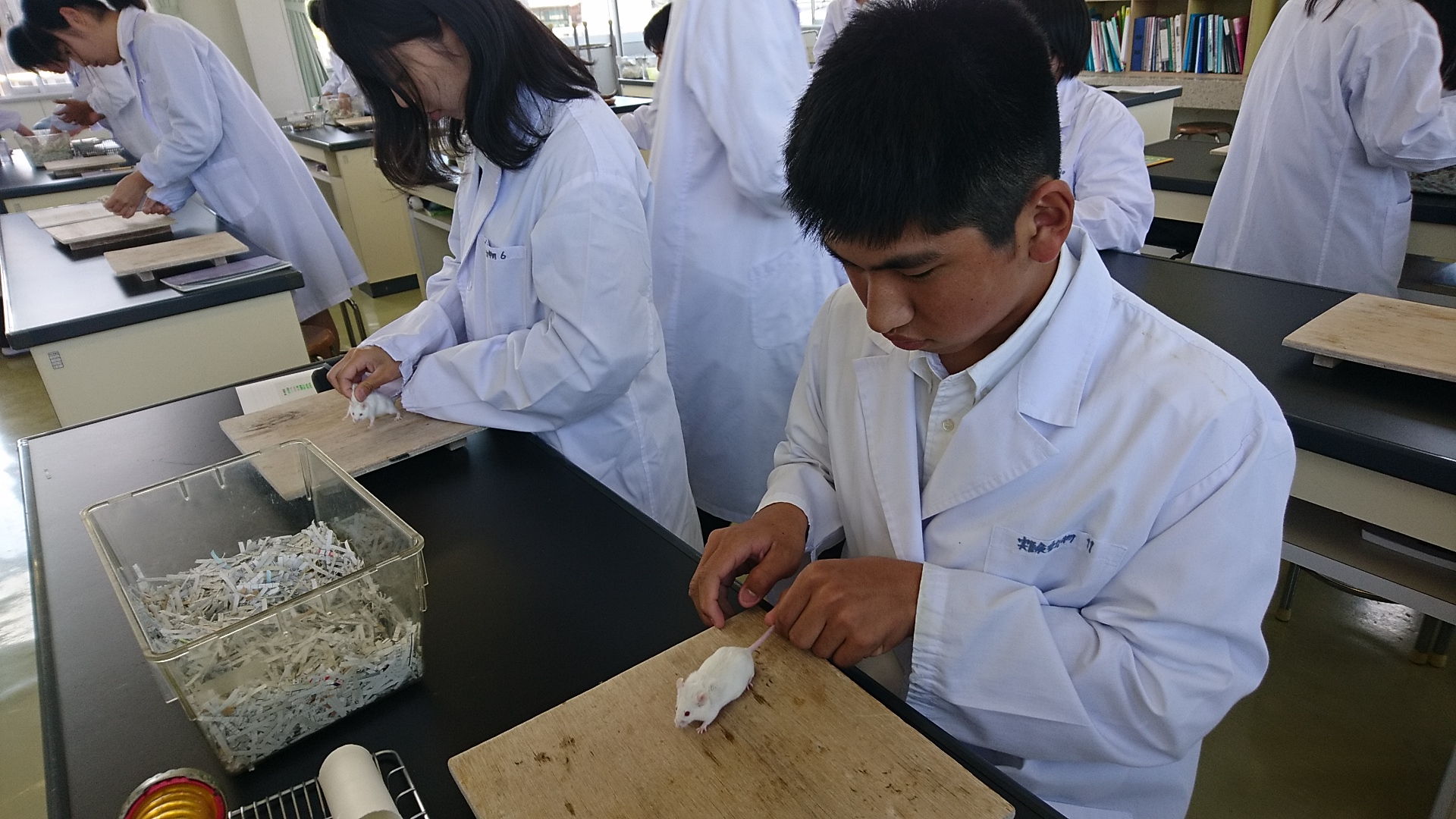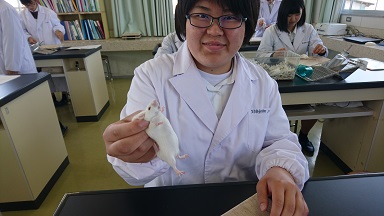みなさんこんにちは畜産科学科中家畜です。
3年生になると課題研究という授業があります、この時間は私たち生徒が1人一つのテーマで1年間研究を続けていきます。そして来年の1月末に研究発表会があります。私は肥育豚にシイタケの粉末を給与して発育や肉質にどんな変化があるのかを調べようと思っています。干しシイタケはうまみ成分の一つであるグアニル酸が多く含まれており、その他にもビタミンD・カリウム・葉酸といった成分も多く肥育成績や肉質向上に期待しています。 通常の飼料に1%の割合で混ぜていきます
通常の飼料に1%の割合で混ぜていきます
 この子達(豚デス)に食べてもらいます
この子達(豚デス)に食べてもらいます
 シイタケの粉末です
シイタケの粉末です














 5月29日、園芸科学科3年園芸セラピー専攻生が、
5月29日、園芸科学科3年園芸セラピー専攻生が、




 写真に写っている子豚の背中に書いてある番号は生まれた順番です、子豚はみんな 同じような顔なので見分けられるように書いています。
写真に写っている子豚の背中に書いてある番号は生まれた順番です、子豚はみんな 同じような顔なので見分けられるように書いています。