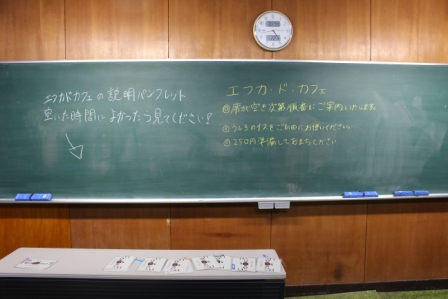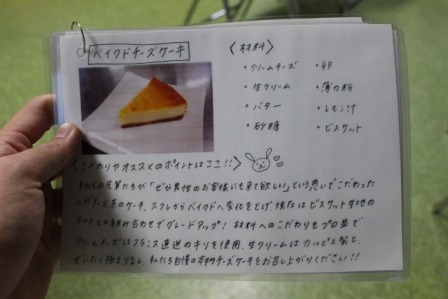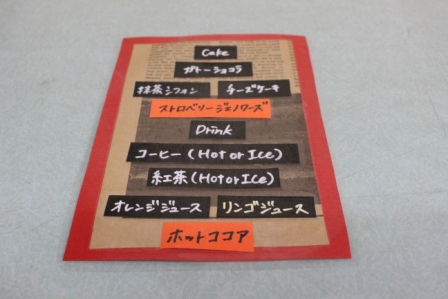12月20日に高大連携学習として食品科学科2年生が、本校で山陽学園短期大学 食物栄養学科の青木 三恵子先生の講演を受けました。
高大連携学習とは、高校生が大学の先生方の講義や実習を受けて専門的な学習をさらに深めていく取り組みです。

「人生を充実して幸せに生きるために」というテーマで、公衆衛生に関するお話しをしていただきました。

「平均寿命と健康寿命」、「シカゴの熱波」、「少子高齢化」等をキーワードにわかりやすく講話して下さいました。
高大連携学習は、生徒が高度な専門教育を大学の先生方から直接学ぶことができます。高校では学べない、貴重な機会となっています。